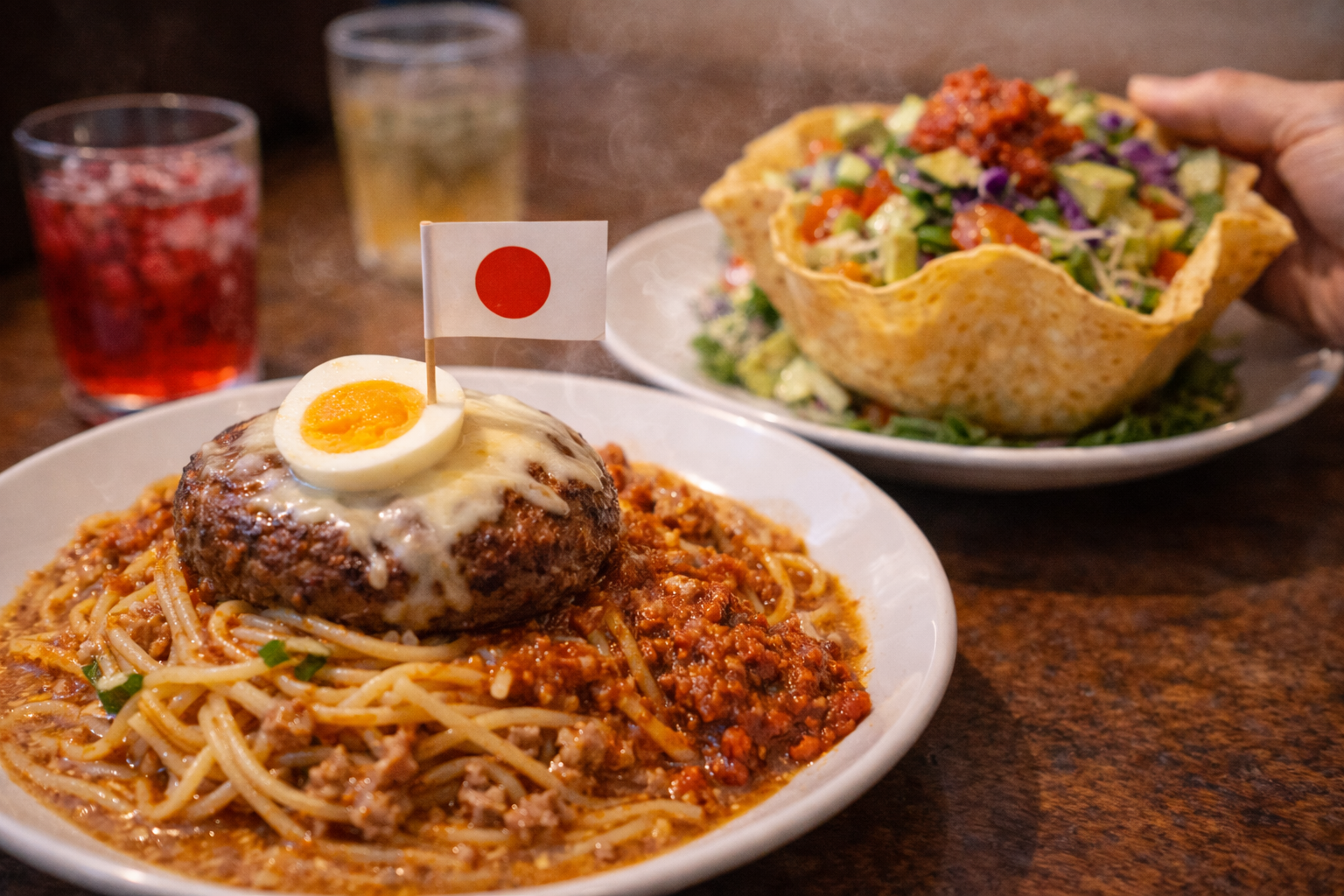【山形・天童市】将棋が息づくまち歩き│マンホールやモニュメントに隠れた駒たち
2025/11/07 ※このサイトには広告が含まれます カテゴリー: 街歩き

山形県天童市は、“将棋のまち”として知られる場所。
駅前のモニュメントや街灯、橋の欄干、商店の看板にいたるまで、まちの随所に将棋駒のモチーフが散りばめられています。
さらに足元に目を向ければ、マンホールにも駒のデザインが。
歩くたびに新しい発見があり、まるで「駒探し」を楽しむようなまち歩きができます。
観光施設の中だけでなく、まち全体が将棋の文化とともに息づいている――。
そんな天童市ならではの風景をご紹介します。
日常に溶け込む、天童ならではの将棋文化

春、舞鶴山の桜が満開を迎えるころ、山頂では「人間将棋」が開催されます。
鎧兜に身を包んだ武者たちが盤上に立ち、観客の歓声が響く――天童ならではの春の風物詩です。
ほかにも学生大会やプロ棋士によるタイトル戦が開かれるなど、天童市では一年を通して将棋にまつわる催しが行われています。
街には職人が営む工房や、駒の実演販売を行う店舗もあり、実際に「駒づくり」の現場を見学することもできます。
また、市内の文化施設では将棋の基礎を学べる体験イベントもあり、初心者でも駒の動きや対局の楽しさにふれることができます。
こうした環境が整っているのは、天童が長い年月をかけて「将棋とともに生きてきた街」だから。
観光客にとっても、地元の人にとっても、将棋は「日常の中にある文化」として息づいています。
駒づくりと天童の歴史

天童市が「将棋駒のまち」と呼ばれる背景には、江戸時代の天童藩の政策があります。
当時、財政難を補うために藩士に副業として奨励したのが「駒づくり」でした。
武士が刀を置き、木を削り、筆をとる――。
その手仕事が次第に地域に広まり、やがて町ぐるみの産業へと発展していきます。
これをきっかけに天童は将棋駒の産地として発展し、やがて全国的にもその名を知られるようになりました。
明治以降には分業体制が整い、職人の手作業による「手彫り駒」に加えて、彫りの工程を機械化した「彫埋(ほりうめ)駒」の生産も広がります。
こうして天童は、国内有数の大量生産地へと成長。
優れた技術力と安定した生産量により、現在では日本一の将棋駒の産地として知られています。
100年を超える歴史を受け継ぎながら、今もなお天童市を象徴する伝統産業としてその技が息づいています。
現在もなお、市内には代々続く駒師の工房や、若い職人たちによる新しい試みが息づいています。
伝統を守りながらも時代に合わせて進化する――。
それが、天童の駒づくりの魅力であり、街全体に流れる“ものづくりの精神”なのです。
天童まち歩きと駒探し
天童の町を歩いていると、いたるところで将棋駒をモチーフにしたデザインに出会えます。
橋の欄干、街灯、案内板、マンホールのふた——その一つひとつに「将棋のまち・天童」の息づかいが感じられます。
観光スポットだけでなく、日常の風景にまで駒の意匠が溶け込んでいるのは天童ならでは。
歩くたびに新しい駒を見つけるような、まるで“まち全体が将棋盤”のような散策が楽しめます。
JR天童駅前
JR天童駅は、「将棋のまち・天童」の玄関口にふさわしい場所です。
駅を出るとすぐに目に入るのは、大きな駒のモニュメントや、将棋をテーマにした装飾。駅前広場全体が将棋一色に彩られています。

駅舎の中には「天童市将棋資料館」や将棋体験ができる交流室もあり、プロ棋士の対局や人間将棋の資料など、将棋文化を身近に感じられる空間になっています。
足元のマンホールにも注目です。
一部には詰将棋の譜面がデザインされており、まるで“歩くだけで将棋の世界に足を踏み入れる”ような体験ができます。
駅に降り立った瞬間から、天童の将棋文化が迎えてくれる――そんな場所です。
舞鶴山
天童のシンボル・舞鶴山(まいづるやま)は、春になると約2,000本の桜が咲き誇る名所として知られています。
この山の山頂には、毎年4月に開催される「人間将棋」の舞台が設けられ、将棋の駒に扮した武者たちが大盤の上で対局を繰り広げます。
駒音と太鼓の響き、そして満開の桜――まさに“将棋のまち・天童”を象徴する光景です。

山頂の広場には巨大な将棋盤が設置され、誰でも記念撮影ができる人気スポットになっています。
また、夜には駒の形をした街灯がほんのり灯り、桜と相まって幻想的な雰囲気に。
昼と夜でまったく違う表情を見せてくれるのも、舞鶴山ならではの魅力です。
天童市役所付近
天童市役所の周辺を歩くと、街灯や案内板、歩道のタイルなど、さりげない場所に将棋駒のモチーフを見つけることができます。
観光スポットのような派手さはありませんが、「将棋が暮らしの一部として根付いている」ことを感じられるエリアです。

古くから設置されている駒型のオブジェのほか、近年ではモダンなデザインの新しいモチーフも登場。
歴史ある街並みに現代的なデザインが調和し、時代を超えて将棋文化が息づいていることを実感できます。
天童を訪れた際には、ぜひこのエリアをゆっくり散歩しながら、街の中に隠れた小さな駒たちを探してみてください。
何気ない通りの中に、意外な発見がきっと待っています。
天童温泉街
天童温泉街を歩くと、いたるところに将棋駒をモチーフにしたデザインを見つけることができます。
旅館の看板や街灯の装飾、案内板など、温泉街全体が「将棋のまち」を感じさせる雰囲気に包まれています。

地元市民の憩いの場所であり、また観光客にも人気の高い天童温泉街には、駒の形の案内板や看板がたくさんあります。
市役所付近から続く倉津川の橋の欄干には、龍王の駒もあり、珍しい発見が楽しめます。そして何気なく通った道路の汚水用のマンホールの蓋に、誤植を発見してしまうというユニークな体験もできます。
あれあれ??実際に探してみたら、「と金」はあるのに「歩」のモチーフが無い?!観光マップにも「歩」の記載はあるのですが、実際に訪れてみると「あゆみばし」との表記があるばかり。。。ちょっと意外でした。
天童のシンボルの駒 縁起物としての願いを込めて

将棋のまち天童には、昔から贈答品に「飾り駒」を贈る風習が根付いています。
新築祝いや開業のお祝い、年齢を寿ぐもの等に将棋の駒に願いを込めていました。よく贈られる人気の駒について説明します。
左馬(ひだりうま)
左馬は、馬の字を逆さにした天童独自の縁起駒です。馬は元来左から乗るものなので、右から乗るとつまずいて転ぶという習性をもっており、そのことから左馬は長い人生をつまずくことなく過ごすことができるとか。また、人が馬を引くのではなく、馬に人が引かれて来ることから千客万来の意味があり、福を招くめでたいもので商売繁盛の守り駒となっています。
さらに、読み替えると「うま」が「まう(舞う)」となり福を呼び込むとされたり、左馬の形が口を絞った巾着の形に似ていることから富のシンボルとして、家内安全のお守りとしても親しまれています。
今でも祝い事や観光のお土産に選ばれる、天童を代表するモチーフです。
王将(おうしょう)
勝負の要となる駒で、守り抜くことが勝敗の条件となります。倒されると負けとなり、将棋の中で唯一無二の存在です。攻めるよりも「生き残る」ことが重要な駒です。
このことから、出世・成功・招福の願いを込めて、天童では左馬とともに縁起駒として贈答品に選ばれる駒となっています。
歩兵(ふひょう):成ると「と金(ときん)」
前に一マス進むだけの小さくて地味な存在ですが、数が多いので序盤から終盤まで戦力になります。成ると「と金」となり、金将と同じ動きができるようになるため、一歩千金ともいわれ侮れない駒です。
最近は天童でも「と金」が富や成功の象徴として、縁起を呼ぶモチーフとして好まれるようになりました。
駒に込められた役割と個性

他の将棋の駒にもそれぞれゲームの中での役割があります。これらの駒をお守り代わりにいつも持っているという話も聞きました。天童の町の中には、このような駒のモチーフも見つけることができます。
ただ「駒の形だな」と眺めるだけでなく、「この駒にはどんな意味が込められているのかな」と想像してみると、散策がいっそう楽しくなりませんか?
そこで、代表的な駒の特徴や動きをご紹介します。
飛車(ひしゃ):成ると「龍王(りゅうおう)」
盤上を縦横無尽に動く最強の攻め駒で、自陣に攻め駒を打たれるのを防ぐ役割も持ちます。大駒(主力攻撃駒)。上下左右に何マスでも動けます。
角行(かくぎょう):成ると「龍馬(りゅうめ)」
斜めに大きく動ける角行は飛車と同じ大駒です。斜め方向にだけ何マスでも動けますが、接戦には弱いともいわれます。
金将(きんしょう)
王を守る最も堅実な駒であり守備の要となります。攻めることより守りに強い駒ですが、接戦に強い駒です。
陣形のバランスを支える役割を持ち、安心感を与える存在です。
銀将(ぎんしょう):成ると「成銀(なりぎん)」
前の他に後ろ斜めにも進める銀将は、金将とともに守りながら攻める駒です。金将に比べると守りに弱いため、攻めに向いているといわれます。
桂馬(けいま):成ると「成桂(なるけい)」
将棋で唯一、他の駒を飛び越えて進めるのが桂馬です。
前にしか進めず、端まで行くと進めなくなるので守りには弱い駒だと言われますが、独特の動きで奇襲を仕掛ける駒として、相手陣営深くに入り込む攻撃の要として力を発揮します。
香車(きょうしゃ):成ると「成香(なるきょう)」
槍をイメージとした、前方一直線にしか進めない直線的な攻め駒です。端の守りや攻めに欠かせませんし、終盤では王将を脅かす攻めをすることもあります。
広がる妄想散歩 ― 『3月のライオン』と将棋のまち天童・島田八段のふるさとを想像して

天童市は、マンガ『3月のライオン』とのコラボ企画でも知られています。作中に登場する島田開八段は、天童市出身という設定ですが、詳しい出身地域は明かされていません。
小さい頃から山に登り、相当な努力を重ねてプロ棋士となった島田八段の姿は、雪深い静かな山里で育った少年時代を想像させます。
実際の天童市も、東側には山を背にした静かな集落が点在しています。
田麦野、津山、貫津、干布など、昔ながらの家々と田園が広がる地域に足を延ばせば、まるで物語の中に入り込んだような感覚に。
作中の島田八段のセリフに「なにもなくなろうとしてるところだよ。人も田んぼも学校も家も…」というセリフは、現在の天童市にも重なります。
新しい街が広がる一方で、少子化により閉校となった学校や人の少なくなった集落もあるのです。
どこが島田八段の出身地なのかは想像の世界に留めておいて、作品の舞台を思い浮かべながら、山々に囲まれたこのような集落を車で巡ってみるのも一つの楽しみ方です。(※野生生物には十分お気を付けください。)
まとめ
実際に天童のまちを歩いてみると、思っていた以上に静かで穏やかな印象を受けます。
将棋駒のモチーフは控えめながら、駅前のモニュメントや街灯、マンホールなど、町のあちこちに確かに息づいていました。
それは“観光のための装飾”というよりも、長い歴史と暮らしの中で自然に溶け込んだ天童の日常そのもの。
将棋がこの町の文化として、そして人々の誇りとして生き続けていることを感じます。
足元の駒、橋の欄干の装飾、そして飾り駒に込められた願い。
どれもが小さなメッセージのように、「この町の時間」を語りかけてくれます。
もし天童を訪れる機会があれば、観光名所を巡るだけでなく、ゆっくりと街を歩きながら “駒探し” を楽しんでみてください。
きっとあなたの目にも、この町が大切にしてきた“将棋の物語”が見えてくるはずです。